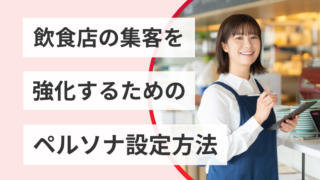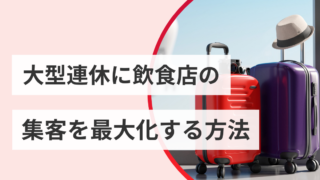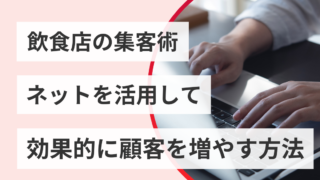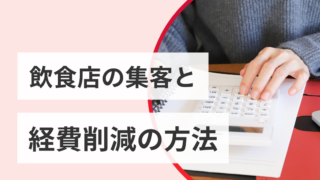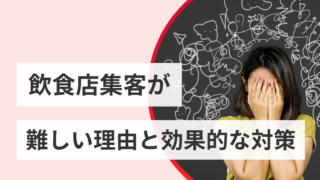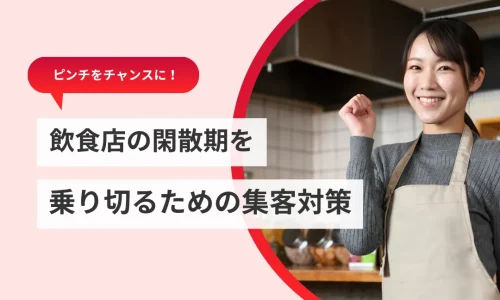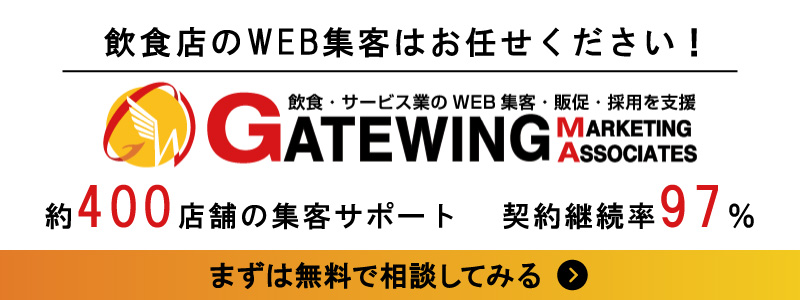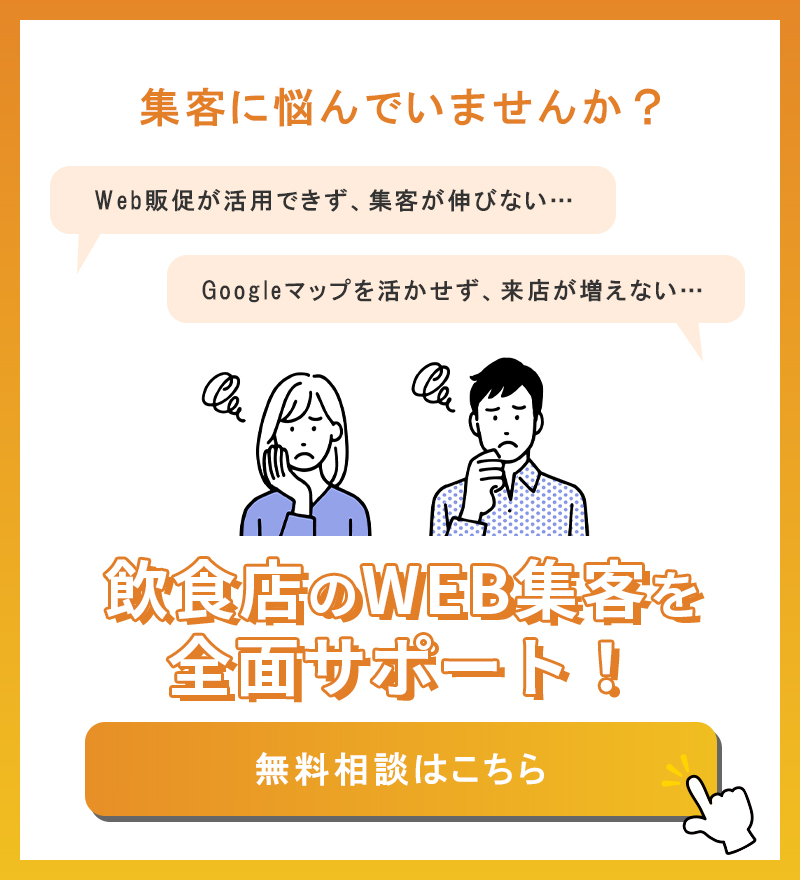新規開店する際や現在のメニューに古さを感じる場合など、メニュー表を作る機会があるでしょう。ただし、商品名と金額を書くだけではもったいない。というのも、飲食店にとってメニュー表は重要な販促ツールの一つだからです。
そこで今回は、メニュー表がどれほど重要なのか、どうすると売上につながるメニュー表を作れるのか、といったことなどをお伝えします。
メニュー表をどう作ればいいのかがわかるようになりますので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
飲食店にとってのメニュー表の重要性
 「飲食店のメニュー表とは」という問いに対して多くの人が、「提供している商品をお客様に伝えるもの」と答えるでしょう。
「飲食店のメニュー表とは」という問いに対して多くの人が、「提供している商品をお客様に伝えるもの」と答えるでしょう。
しかし実際は、メニュー表にはそれ以上の役割があります。その重要性について述べてまいります。
お客様にコンセプト・ウリを伝え、安心感を与える
まずは、特に初来店のお客様に対してですが、どのようなお店なのかを伝える効果があります。
かしこまったお店なのか、ざっくばらんなお店なのかといったことが、メニュー表の質感や商品名、使っている字体、金額などで自然にわかってもらえます。お店のコンセプトを従業員が一から説明することはむずかしいですが、メニュー表なら労力をかけず表現可能です。すると、お客様はこのお店ではどう振る舞うべきなのかがおおよそわかります。
人は環境に合わせて行動しようとするものです。しかし、コンセプトが伝わらなければ、どうしてよいのかがわからず不安になります。お店の看板商品やウリをメニュー表で伝えるのも、不安を払しょくするための一環といえるでしょう。
メニュー表はお店についての情報を伝え、お客様に安心感を与えるツールです。
それだけに、お店のコンセプトと離れたメニュー表を作ると、お客様を混乱させてしまいます。メニュー表は外観に次ぐお店の顔だと思って作るようにしましょう。
売上を左右する
メニュー表によってお客様の注文は変わってきます。
商品を金額の低い順に並べただけでは、最初の一番安い商品ばかりが注文されるかもしれません。しかし多少高くても、おすすめ商品を最初に置き、説明もしっかり書けば、多くの人がその商品を注文するでしょう。
メニュー表はメニュー表の作り方ひとつで、お客様の行動は変わります。
お客様に喜ばれ、お店の利益にもなるメニュー表作りを心がけてください。
売上につながるメニュー表の作り方
 メニュー表が売上に影響するとお伝えしましたが、具体的にどのような作り方をすればよいのでしょうか。
メニュー表が売上に影響するとお伝えしましたが、具体的にどのような作り方をすればよいのでしょうか。
以下に一般的な流れを説明していきます。
メニュー表の形体を決める
お店の業態やコンセプトによって、お客様に受け入れられやすい形体は変わってきます。
例えば、高級料亭がラミネート加工された1枚もののメニュー表というのでは、しっくりこないでしょう。また、1,000円でおつりがくるような大衆居酒屋で、本革のメニューブックというのも違和感があります。
まずは、お店にとって違和感のないメニュー表を選ぶところから始めましょう。
レイアウトを考える
次に、どこに何を載せるか、大きさはどうするかといったレイアウトを考えましょう。
業態やコンセプトに合わせたレイアウトにする
業態によって基本的なレイアウトがありますので、それをベースに考えましょう。
例えばお蕎麦屋さんの場合、最初に最もシンプルな「かけそば」があり、それから価格順に具材別の商品が並ぶというのがオーソドックスです。これは、お客様が好みや予算に合わせて注文を決めやすいというメリットがあるからです。
また、レストランであれば、はじめに前菜があり、スープ、メイン、デザート、コーヒーといった順が一般的でしょう。これは、お客様が料理を食べる順番に沿っていて、食事の流れに合わせて注文するのに適しています。
他にも、お店のコンセプトによってお客様が注文しやすいレイアウトが分かれます。これらを踏まえてメニュー表作りを進めましょう。
特定の商品が目立つようメリハリをつける
業態などに合わせてレイアウトの基本が決まることを紹介しました。しかし、このレイアウトに沿っただけのメニュー表では不十分だといえます。
というのも、お店の独自性が出せないからです。お店にはそれぞれの看板商品やイチオシの商品などがあるはずです。しかし基本レイアウトどおりでは、それが伝わりにくいことが多いでしょう。
これらの商品は、他のお店にはないあなたのお店の魅力が発揮されたものであり、注文していただくことはお店にとってもお客様にとってもメリットになるはずです。それであれば、わかりやすくお客様に伝える必要があります。
横書きのメニュー表であれば左上、縦書きであれば右上が最初に目に飛び込んでくる場所ですから、目立たせたい商品はそこに載せましょう。また、掲載スペースも大きいほど目につきますので、他の商品とのバランスを取りつつ大きめに掲載してください。
他にも、各カテゴリーの最初に目玉商品や注文してほしい商品を大きく載せることも有効です。
商品名等をお客様の心に引っ掛かりやすくする
時折、一般的な商品名だけを載せているお店がありますが、これはもったいないといえるでしょう。なぜなら、お客様の注文意欲を高められず注文点数が増えにくいばかりでなく、特徴のないお店だと思われて次の来店につながらない可能性もあるからです。
お客様に注文したいと思わせ、次も来たいという気にさせる表記をしましょう。
商品名にフックを作る
商品名は他の商品と区別するためだけにあるのではありません。キャッチコピーのようなものであり、これを見るだけで注文したいと思ってもらうことが理想です。
そのためには、この後にお伝えする説明文に必要な要素を適度に入れるとよいでしょう。ただし、長すぎると逆に読む気がなくなってしまうので、コンパクトにまとめるようにしてください。
シズル感などで興味を引く説明文を入れる
商品名だけで伝えきれない魅力は、説明文を入れてお客様に伝えましょう。その時に、入れるとよい要素がいくつかありますので、順にお伝えします。
①シズル感
料理などで我々の五感に訴えてくる要素をシズル感と呼びます。つまり、視覚や嗅覚、味覚、触覚、聴覚を文字で刺激して、あたかも目の前にその商品があるかのように感じさせるのです。それぞれの例を挙げておきます。
みずみずしい野菜や身の透き通ったイカなど、視覚から鮮度やおいしさが伝わるものは、その見た目の特徴を伝えましょう。
ちなみに、この後紹介する写真とセットにすることでその効果が上がりますので、写真が使える場合は相乗効果を狙ってください。
〈香り〉
焼き立ての香ばしさや食材の持つかぐわしさなど、鼻孔をくすぐり食欲を搔き立てる匂いについて、上手く言葉で表現してみてください。
〈味と食感〉
濃厚な味わいや口に入れた瞬間の感触など、今すぐにでも口にしたいと思えるような、際立った魅力があるのなら文字でそれを届けてみましょう。
〈音〉
グツグツと煮えている、ジュージューと焼けている、このような音も私たちにとってはごちそうの一部です。擬音だけでなく様々な形でおいしい音を再現してみてください。
②素材
こだわりの素材を使っていれば、ぜひそれを伝えてください。同じ商品でも、素材の良さを伝えるだけで食べたいという気持ちが強くなります。また、食べたときの満足度も高くなりますので、素材の特徴を伝えるようにしましょう。
③産地
産地がわかっているもののほうが、安心感があり、期待度も高くなります。産地を伝えられるものであれば、極力産地の表示もしていきましょう。
④季節感
食から季節を感じることに喜びを感じる人は多いでしょう。ただし、説明なしで食材や料理から季節を感じられるという場合は少ないものです。常識的にわかりそうだと思っても、一言添えると良いのではないでしょうか。
⑤限定性・希少性
例えば、提供数が少ないもの、なかなか口にできないものなどは、人の興味を引きやすいものです。そのような珍しいものであれば、メニュー表でもしっかり提示してください。
⑥作り方
調理過程を示すことは、料理のイメージが湧きやすく食べたいという気を起こさせるものです。特に、お客様から調理風景が見えない場合には、安心感にもつながりますので、作り方も伝えるようにしていきましょう。
お客様に訴求する写真を入れる
先ほども述べたように、写真は見た目を伝えるのに大きな力を持っています。多くの言葉も、たった1枚の写真にはかなわないのが普通です。
しかし、すべての商品に写真を使うとメニュー表のボリュームが大きくなってしまい、注文しづらくなることもあります。ですから、注文を集めたい商品、文字で表現するのが難しい商品など、使うところは工夫してください。
また写真を使う場合には、注文したくなるような写真を使用しましょう。自分で撮影する場合には、以下のポイントを押さえてください。
自然光に近い色で明るめに撮ると食材の彩りが映えます。また、カメラの反対側から光を当てて、料理の表面で反射させると照りが出て、みずみずしさやジューシーさを出すことが可能です。
〈画角〉
画角は、料理全体を写すとどのような料理かを説明するのに適したものとなり、近くに寄ったものでは食感や味わいなどを想像させるのに向いています。
あとは、出来立てのおいしさを表現するためには、作ってすぐに撮影するのがベストです。料理を作る前に、構図やライティングなどをすべて固めたうえで、調理にとりかかるとよいでしょう。
メニュー表を作る際の注意点

以上で、お客様が注文をしたくなり、売上につながるようなメニュー表作りができるはずです。ただし、メニュー表を作っているうちについ忘れてしまうかもしれないことがありますので、いくつかお伝えさせていただきます。
お客様の知識を過信してしまう
例えば食材の旬や肉の部位、調理法など、お店の人にとっては当たり前のことでも意外とお客様にはわからないものです。知っているものだと思わず、お客様は知らないかもという視点でメニュー表を作りましょう。
デザインに凝り過ぎてしまう
かっこいいメニュー表を作ろうとがんばっているうちに、デザインに凝り過ぎることがあります。たしかに美しいメニュー表は見ていて楽しくなるものですが、わかりづらくなっては逆効果です。見やすさ、注文のしやすさを忘れないようにしてください。
誇張してしまう
これは写真を撮影する時に起こりがちなのですが、実際に提供するものより多めにしたり、本来使わない食材を追加してみたりと実物以上にしてしまうものです。写真を見て注文したお客様が実物を見てガッカリということがないように、気をつけましょう。
今回は、飲食店にとってメニュー表がいかに重要かをお伝えし、メニュー表の作り方や作る際の注意点などを解説してきました。メニュー表は、単にメニューを羅列するものではなく、お店のことを知ってもらい売上につなげるものだというのがご理解いただけたかと思います。
しかもメニュー表は一度作ればしばらくは使い続けられますので、しっかり作っておけば売上に貢献し続けてくれるという費用対効果にも優れているものです。
じっくり取り組んで、大きな成果につながるすばらしいメニュー表を作ってください。